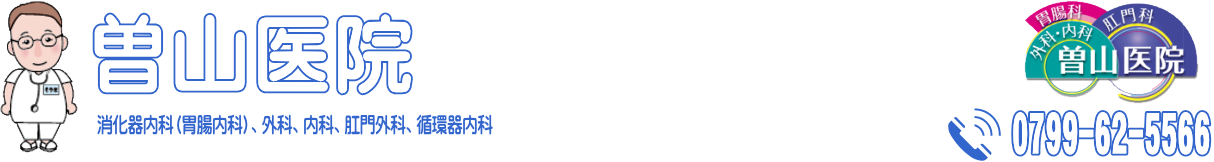利用者(利用者のご家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいて頂きたい内容をご説明します。わかりにくいことがあれば、遠慮なくご質問下さい。
1.当事業所が提供するサービスについての相談窓口について
電話 (0799)-62-5566 FAX (0799)-62-5577
| 営 業 日 | 月曜日~土曜日 (日・祝・8/13~15・12/29~1/3は休み) |
| 営業時間 | 8:00~18:00 (但し木・土は12:00まで) |
| 担 当 | 曽山 信彦 |
2.当事業所の法人概要について
| 法人格・名称 | 医療法人社団 曽山医院 |
| 所 在 地 | 兵庫県淡路市志筑1391-9 |
| 連 絡 先 | 電話:0799-62-5566 FAX:0799-62-5577 |
3.利用者に居宅介護支援サービス提供を担当する事業所について
(1) 事業所の所在地等
| 事業所名 | 医療法人社団 曽山医院 |
| 所 在 地 | 兵庫県淡路市志筑1391-9 |
| 連 絡 先 | 電話:0799-62-5566 FAX:0799-62-5577 |
| 事業所の指定番号 | 兵庫県指定 2811600937 平成12年4月1日指定 |
| 事業開始時期 | 平成12年4月1日 |
| サービスを提供する実施地域 | 旧津名町・旧一宮町 |
(2) 事業の目的および運営方針
| 事業の目的 | 利用者が、可能な限りにおいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
利用者やご家族の希望等に合わせご利用になる居宅サービス等の種類及び内容、居宅サービス計画書を作成し、計画通りに各サービスの提供が確保されるよう各サービス事業者等との連絡調整その他の便宜、提供を行います。また、利用者が介護保険施設への入所を希望される場合は、介護保険施設への紹介等の便宜の提供を行います。 |
| 事業の方針 | 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 |
4.当事業所の従業員について
| 事業所の管理者 | 主任介護支援専門員 曽山 信彦 |
| 職種 | 員数 | 業務内容 | 勤務体制 |
| 介護支援専門員 | 4名 | ①要介護(支援)認定申請に対する代行・援助
②居宅サービス計画書の作成 ③サービス事業者との連絡・調整 ④サービス実施状況把握・評価 ⑤利用者の状況の把握 ⑥給付管理 ⑦相談業務 |
常勤4名 |
5.提供するサービスの内容と料金について
(1) サービス内容
上記業務内容に準ずる。
(2) 料金 【厚生労働大臣の定める基準額】
居宅介護支援費(Ⅰ) ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45件未満である場合
| 要介護1・2 | 1,086単位/月 |
| 要介護3・4・5 | 1,411単位/月 |
居宅介護支援費 (Ⅱ) ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45件以上60件未満の部分
| 要介護1・2 | 544単位/月 |
| 要介護3・4・5 | 704単位/月 |
居宅介護支援費 (Ⅲ) ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が60件以上の部分
| 要介護1・2 | 326単位/月 |
| 要介護3・4・5 | 422単位/月 |
加算
| 初回加算 | 300単位 | 次のような場合に算定されます。 イ 事業所において新規に居宅サービス計画を作成する場合 ロ 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 ハ 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 |
| 特定事業所加算Ⅲ | 323単位 | 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上及び常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置している場合で、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービスを作成する、質の高いケアマネジメントを実施している場合に加算されます。 |
| 入院時情報提供加算(Ⅰ) | 250単位 | 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、該当利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合に加算されます。 入院した日に情報提供を実施した場合 ※入院日以前の情報提供を含みます。 ※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含みます。 |
| 入院時情報提供加算(Ⅱ) | 200単位 | 入院した日の翌日又は翌々日に情報提供を実施した場合 ※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日ではない場合は、その翌日を含みます。 |
|
退院・退所加算 カンファレンス参加有(1回目) |
600単位 |
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に加算されます。ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限ります。 |
| 通院時情報連携加算 | 50単位 | 利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に、1月に1回を限度として加算されます。なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行います。 |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位 | 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合、1月につき2回を限度として加算されます。 |
注1)介護保険が適用される場合は、以上の報酬は直接介護保険から事業所に給付されます。
減算
| 項目 | 単位 | 利用料 |
| 特定事業所集中減算 | -200 | -2,000円/月 |
| 業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1%に相当する単位数を減算 | |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%に相当する単位数を減算 | |
| 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント | 所定単位数の95%に相当する単位数×地域単価 | |
| 運営基準減算 | 所定単位数の50%に相当する単位数を減算 | |
| ※運営基準減算が2月以上継続している場合、所定単位数は算定しません。 | ||
| 項目 | 算定要件 |
| 特定事業所集中減算 | 正当な理由なく、事業所において前6月に作成した居宅サービス計画に位置付けられた居宅サービス等が特定の事業者に偏っている場合であって、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に減算されます。 |
| 業務継続計画未実施減算 | 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算します。
※1年間の経過措置期間中に事業所で計画がされるよう、令和7年3月31日までの間の減算はありません。 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に基本報酬を減算します。 |
| 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント | 介護支援専門員が行う居宅介護支援業務において、適切なサービスが行われず、厚生労働大臣が定める減算基準に該当する場合、当該月の居宅介護支援費から減算されます。 |
| 運営基準減算 | 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合において、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に減算されます。 |
6.その他の費用について
| 交通費 | 利用者のお宅が当事業所の通常の事業実施地域以外にある時は、交通費はその実費を頂きます。
自動車を使用した場合:1kmあたり100円 |
| 複写物の交付 | 1枚につき20円。 そのつどお支払い下さい。 |
| サービス実施のために利用者のお宅で使用する電話料金 | やむを得ずお宅の電話を使用した場合、利用者の負担となります。 |
7.担当者(介護支援専門員)について
(1) 介護支援専門員の利用者宅への訪問頻度の目安について
当事業所の介護支援専門員が、利用者の状況を把握するために、おおむね月に1回、お宅を訪問します。
また、利用者からご依頼がある場合や、居宅介護支援業務の遂行のうえで不可欠であると認められる場合で利用者の承諾を得た場合は、介護支援専門員は利用者のお宅を訪問します。
(2) 介護支援専門員の変更
- 担当の介護支援専門員の変更を希望される場合は、相談窓口の担当者までにご連絡下さい。
- 事業者側の都合により介護支援専門員を交代させる場合は、交代の理由を明らかにし、交代後の介護支援専門員の氏名を利用者に通知します。
(3) 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証明証を携帯し、初回訪問時および利用者またはそのご家族から求められた時は、いつでも身分証明証を提示いたします。
8.事業者の責務について
(1) 居宅介護支援の提供内容の記録について
利用者に提供したサ-ビス提供の記録は、利用者の要介護認定等の満了日から5年保管します。記録については、利用者とそのご家族に限り、閲覧及び写しの交付が可能です。
(2) 秘密保持と個人情報(プライバシー)の保護について
当事業所及び従業員がサービスを提供する際に、利用者やご家族に関して知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサービスを提供するために、サービス担当者会議等で、利用者もしくはご家族の情報を使用します。その際、同意書に署名をいただきます。
なお、利用者のご家族からの希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知をご家族にも行う場合があります。
- 事故発生時の対応及び賠償責任について
- 当事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。
- 当事業所の責任において、利用者の生命・身体・財産などを傷つけた場合は、事業所は利用者にその損害を賠償いたします。
- 当事業所が加入している賠償補償制度の内容詳細についてお知りになりたい場合は、当事業所管理者までご連絡下さい。
- 居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業所の選定方法については、複数の居宅サービス事業所を提示し、各事業所に関する情報提供(内容、利用料等)を行ったうえで選定できるよう支援します。
9.業務継続計画の策定等について
(1) 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
(2) 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。研修及び訓練は年2回以上実施、研修に関しては採用時にも実施)
(3) 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
10.衛生管理等について
(1) 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業者は、当該事業所において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
② 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。
③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。(研修・訓練は年2回以上実施、研修に関しては採用時にも実施)
(4) 必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
11.身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為について
(1) 事業者は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行いません。
(2) 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
(3) 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性に留意して、必要最低限の範囲内で行うとともに、身体的拘束等の廃止に向けての取り組みを積極的に行います。
(4) 事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を1月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
②身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。
③従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。(採用時及び年2回以上)
12. 虐待の防止について
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。)を1月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2) 高齢者虐待防止のための指針の整備をします。
(3) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
(採用時及び年2回以上)
(4) 上記(1)~(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を選定しています。
| 虐待防止に関する担当者 | 管理者 曽山 信彦 |
(5) サービス提供中に、当該事業所の従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村等に通報します。
13.契約の解約について
(1) 利用者からの契約解約について
- 利用者は当事業所に対し解約する日の7日前までに事業所に申し出ることによって、この契約をいつでも解約することができます。
- 次の場合は、利用者は事業者に申し出を行うことによって、事前申し出の期間なしに、この契約をいつでも解約することができます。
- 事業者が正当な理由なしに居宅介護支援の提供を行わない場合。
- 事業者が守秘義務に反した場合。
- 事業者が利用者やそのご家族に対して契約を継続しがたいほどの重大な社会通念を逸脱する行為を行った場合。
- 事業者が破産、その他事業者がこの契約に定める居宅介護支援の提供を正常に行い得ない状況に陥った場合。
- 解約料は無料です。
- 事業者からの契約解約について
当事業所は、事業の廃止や縮小によりサービスの提供が困難となった場合など、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して契約終了日の1ヶ月前までに理由を示した文書でお知らせすることにより、契約を解約することができます。この場合、当事業所は他の居宅介護支援事業所に関する情報をお伝えするなど、利用者が続けて滞りなく介護保険を利用してサービスを受けることができるように支援します。
ただし、次の場合には、1ヶ月以上の事前の申し出期間なしに、この契約を解約することができます。
- 利用者がこの契約に定める利用料金等の支払いを3ヶ月以上滞納し、文書による支払い催促を行ったにもかかわらず、催促の日から14日以内にその支払いがなかった場合。
- 利用者もしくはそのご家族による契約を継続しがたいほどの重大な行為により円滑なサービスが提供できなくなる場合(この場合は解約する理由を示した文書を利用者にお渡しします)。
14.契約の終了
次の場合には、自動的に契約は終了いたします。
- 利用者が特定施設入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護の受給を開始した場合。
- 利用者が身体障害者療護施設等の介護保険の被保険者としての資格を失う施設へ入所した場合。
- 利用者の要介護認定区分が、要支援・自立と認定された場合。
- 利用者が当事業所の営業ができない程遠くに移転された場合。
- 利用者がお亡くなりになった場合
15.緊急時の対応
サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医にご連絡するとともに、必要な対応を行います。その際、予め指定する連絡先にも連絡します。
16.相談・苦情窓口
当事業所が提供するサービスについてご相談や苦情がございましたら、下記の窓口まで遠慮なくお申し出ください。
| 医療法人社団曽山医院相談・苦情窓口 | 兵庫県淡路市志筑1391-9 電話番号 0799‐62‐5566 FAX 番号 0799‐62‐5577 受付時間 午前8時00分~午後6時00分(木・土は12時まで) 管理者 曽山 信彦 |
| 兵庫県国民健康保険 団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 |
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9-1-1801号 電話番号 078‐332‐5617 FAX 番号 078‐332‐5650 受付時間 午前9時00分~午後5時15分 月~金(祝日は除く) |
| 淡路市役所 長寿介護課 介護保険係 |
所在地 兵庫県淡路市生穂新島8 電話番号 0799-64-2511(直通) 受付時間 8:30~17:15 月~金 (祝日は除く) |